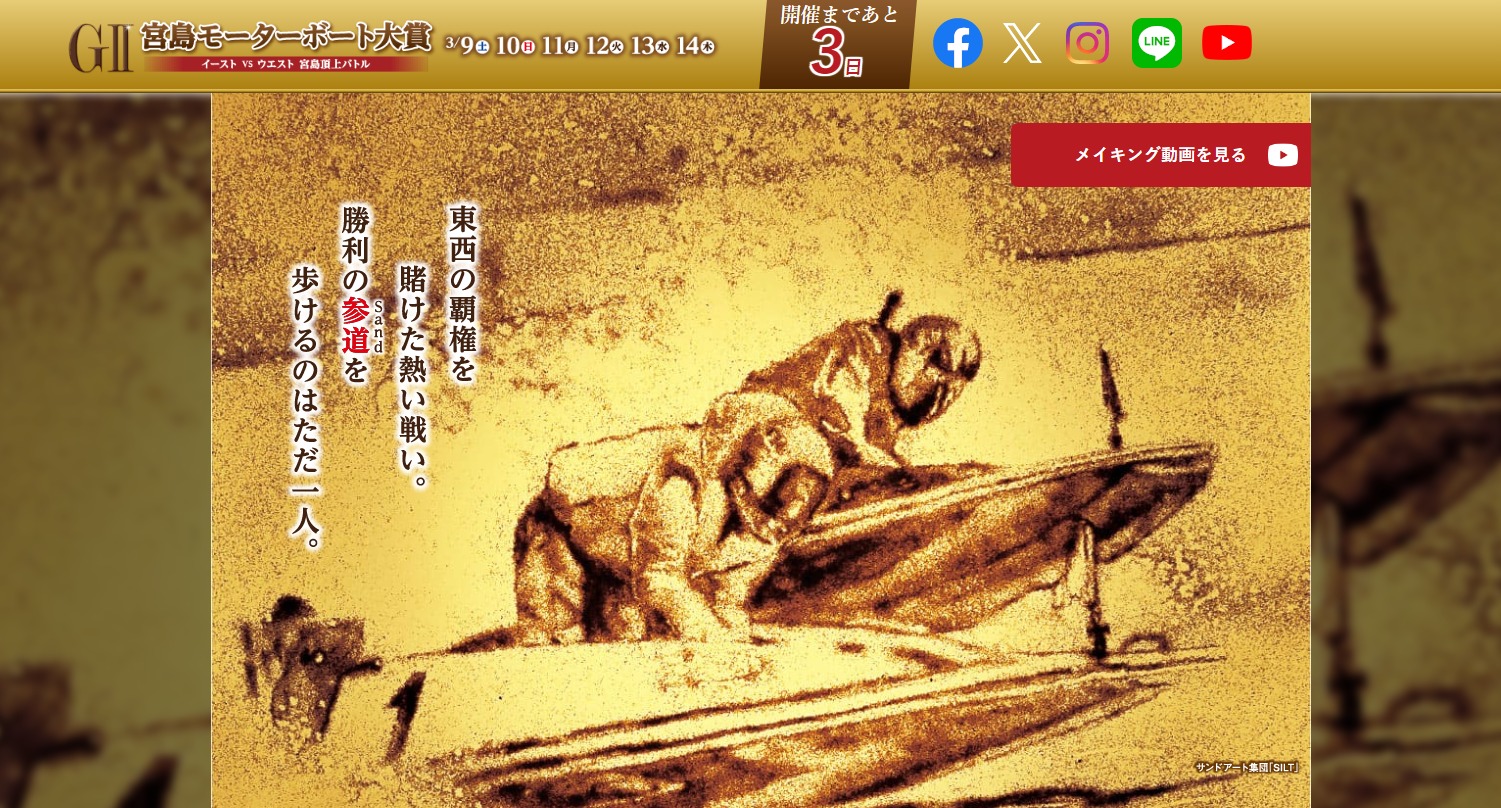三度目の緊急事態宣言が延長された。既に発表されていた東京、大阪、京都、兵庫は延長。
さらに対象地域に愛知と福岡も加えられ、この先のボートレースの開催にも制限が増えてくることは避けられない。
それでも開催が行われているのは唯一の救いだ。
そんなコロナ禍の影響で、ボートレース界でも緊急事態とも言える問題が発生した。
それが選手による持続化給付金の不正受給問題である。
今回は順を追ってこの問題について流れや出来事を整理し、その対応の是非を考える。
持続化給付金とは
まず前提となる持続化給付金について簡単に説明しておきたい。
持続化給付金は「コロナウイルスの感染拡大により、仕事のキャンセルや営業自粛になった事業者やフリーランス、個人事業主に、事業の継続を支え、再起の糧にしてもらうための資金であり、中小法人なら最大200万円、個人事業主やフリーランスなら最大100万円を国が給付してくれる制度」のこと。
給付であるため返済をする義務でない。個人事業主への給付には
②“新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で“前年同月比で収入が50%以上減の月があること。
と、この2つの要件が必要である。
なお、この持続化給付金という制度は2021年には規模や額面が縮小され、一時支援金や月次支援金として引き続き同様の対象者に給付されている。
例:年間120万(月10万円)の稼ぎがあり、コロナ禍の影響で月4万円しか貰えなかった場合。
例のように月10万円の収入でも限度額に近いような給付となり、生業が影響を受けていた場合は一律100万円給付となっていることも予想される。
制度には問題点もあり、申請してから給付まで数ヶ月振り込まれず、その間を凌げずに廃業となってしまうこと。そして今回とり上げる不正受給の問題等がある。
経済産業省では「不正受給は犯罪」という文言と共に注意喚起を促していた。
発端
きっかけは2月半ば。JRA(日本中央競馬会)の騎手や厩務員が持続化給付金の不正受給をしていたとして大々的に報道された。
これは馬主でもあるとされる関西の男性税理士が持続化給付金の受け取りをサポートする旨のビラを配布して、関係者らに申請を促し、報酬も得ていたとの報道もあった。
この税理士に普段の業務を委託している者もおり信頼は厚かった。このコロナ禍においてJRAは開催中止をしていない。
だが「税」つまりお金に関するプロフェッショナルなのだから、申請要件を満たす角度の見方をアドバイスし、それによって減収したという内容で申請することは可能であった上に、信用をおけるのではないかと思う。
※あくまでも憶測だが、JRAにおけるコロナ禍の影響の1つに「土曜日と日曜日は原則として同じ競馬場で騎乗しなければならない」といった事象があった。これによって日曜日にG1が開催となれば、土曜日に他場で開催の重賞に騎乗できないという点がある。(もちろんレース結果によって収入は大きく変わるが)このことも「影響」と言えるか否かは素人の私には判断が出来ない。
JRAは2月16日に100名ほどの関係者が不正受給した疑いで事実関係の確認を進めた。
これを受ける形で日本モーターボート競走会と日本モーターボート選手会でも3月10日より実態調査を開始した。
記者会見

3月30日
日本モーターボート競走会会長の潮田政明氏は冒頭で「調査の結果、211名の選手が持続化給付金制度の趣旨を十分に理解せず、個人事業者として、安易に受給できると判断し、申請手続きを行っていたことが分かりました。」と発した。全文引用しては長くなるため、要点だけを箇条書きの形で引用する。
・アンケートは全選手1574人に実施
・受給理由はレース打ち切りによる収入の減少
・打ち切り分は追加斡旋を行っており影響は限定的
・フライング辞退期間を申請理由としているかは精査中
・2020年7月に不正受給の噂があり注意喚起文書を全選手に出した
・申請時期(注意喚起の前と後等)は精査中
・受け取った選手には返還手続きを行うよう指示
会見での発言の順序は異なるが要点となるのはこのあたりか。この時点で1割以上の選手が受給申請を行っていたといことがわかった。
会見において「今後、厳正に対処、指導を徹底していく所存でございます。」とも潮田氏は話している。
4月28日
3月30日の会見以降、翌日の3月31日から4月12日の間、記名式の調査を実施。精査期間中に新たに4名が受給を申告し、以下のような精査結果となった。
受給総額 2億1,473万円
返還者数 215名(手続中含む)
返還総額 2億1,473万円
受給申請時期 令和2年5月1日~令和3年2月15日
受給申請理由
[1]フライング又は出遅れによる 24名
[2]私傷病及び公傷等による 43名
[3]感染者や濃厚接触者等に指定され、或いは開催中止や打ち切りとなり、出場あっせんに影響を受けたことによる 67名
[4]感染症拡大予防等のため、競走不参加、前検不合格、途中帰郷となったことによる 68名
[5]ボートレース以外の事業収入等による 13名
受給者の属性
[1]級別(A1級43名、A2級39名、B1級110名、B2級23名)
[2]性別(男子200名、女子15名)
[3]年代別(20代46名、30代94名、40代50名、50代23名、60代2名)
また、会見の要点は以下の通り。
・選手の1割が受給したのは持続化給付金制度に関する理解不足と、選手一人ひとりのモラル・コンプライアンスに対する認識の低さが一番の要因
・収入が半減している要件のみで申請出来ると思い込んでいた選手もいる
・故意性のある選手は見受けられなかった
・今回の受給はモラルに反するだけではなく、「不正に繋がりかねない行為」
・業界のペナルティである「フライング辞退」を申請理由としたことは、業界として最も不道徳
・副業での収入による申請も不適切
・「不正」であるか等については中小企業庁の判断
・受給した全選手は既に給付金を返還済若しくは返還手続中
・再発防止に努める
これら精査を受けて4月27日に行われた褒賞懲戒審議会の諮を経て、褒賞懲戒規程第11条第5号「選手としての体面を汚し又は著しく風紀を乱したとき」に該当するとして、以下のとおり処分を決定した。この処分は5月1日より適用となった。
調査結果と処分
(1)新型コロナウイルス感染症の影響が無い「フライング又は出遅れによる」理由で、選手会による注意喚起以降に受給していた、11名:「出場停止4ヶ月」
(2)新型コロナウイルス感染症の影響が無い「フライング又は出遅れによる」理由で、選手会による注意喚起以前に受給していた、13名:「出場停止3ヶ月」
(3)新型コロナウイルス感染症の影響が無い「私傷病及び公傷等による」理由で、選手会による注意喚起以降に受給していた、19名:「出場停止2ヶ月」
(4)新型コロナウイルス感染症の影響が無い「私傷病及び公傷等による」理由で、選手会による注意喚起以前に受給していた、24名:「出場停止1ヶ月」
(5)新型コロナウイルス感染症の影響が有り、「感染者や濃厚接触者等に指定され、或いは開催中止や打ち切りとなり、出場あっせんに影響を受けたことによる」、「感染症拡大予防等のため、競走不参加、前検不合格、途中帰郷となったことによる」、「ボートレース以外の事業収入等による」という理由で受給していた、148名:「戒告」
JRAの対応

発端となったJRAに関連する者への処分は再調査の結果、受給者は4名増えて169名(うち3名は副業の収入減などによる申請)。
調教師22名=延べ24名(重複含む) 戒告、厳重注意、注意
厩舎従業員135名のうち132名(退職者含む) 厳重注意
厩舎従業員 残り3名 5日間の出勤停止(当初の調査に対して虚偽の回答をしたため)
長期の出場停止処分はなかった。また関与が疑われた税理士については処分することができないとしてお咎めなしとなっている。これに対し各方面から「甘すぎる」といった声が高まっている。出場停止はもとより減給などの対応もない。戒告処分は「厳重注意を言い渡す」というだけで処分としては確かに軽いものだ。
※参考
最近の公営競技の不正となると笠松競馬の関係者が馬券購入していたとされる問題が挙げられる。
4名が競馬法違反で書類送検され最も重い「競馬関与禁止」となり、この4名に対し情報提供をし金品を受け取っていたなどで、騎手と調教師計8名が半年から5年間の競馬関与停止となった。この処分を受けた8名に関しても競馬法により、騎手免許·調教師免許が取り消される。
また、監督すべき調教師に対し一定期間の「賞典停止=賞金を受け取れないこと」となることも発表された。この問題について、直接関わっていなかったものの、「不正行為等報告違反」として残り全ての9騎手が戒告処分となっている。
この件に関しては行政手続法である競馬法に違反しており、モラルやコンプライアンスとは次元の違う話であるが、参考までに掲載しておく。
ボートレーサーへの処分は相当か重すぎか
率直な感想としては重すぎると感じた。それと同時に処分内容に疑問も残る。
まずはボート界が調査に乗り出す発端となったJRAの件を引き合いに出したい。
モラルなどは別として税理士が申請をアドバイスできたということは、制度上に少なからず問題があったはずだ。
コロナ禍では多くの人に多かれ少なかれ影響は及んでいる。貰える給付金ならもらいたいと思うのが当然ではないだろうか。
それを返還までした上に出場停止=職を失わさせるというのは、選手に対し一層の苦労をかけている。
先に処分を発表したJRAが甘すぎるという批評を受けた。その動きを受けて世間体を考慮して厳罰となったように思える。
持続化給付金を不正であると認識した上で意図的に受け取った場合は詐欺罪となる。
しかし、4月28日の会見でも「故意性のある選手は見受けられなかった」と発表しているだけに罪に問われることはない。モラルやコンプライアンスを問題とするにしても、受け取れているということは国として問題ないとされたからこそ給付されているのだ。
また、税理士が受け取れると判断して判断ができる制度。プロが可能としているのであれば、我々も含めて素人なら受け取れるのではないかと、制度の仕組みを十分に理解しないまま申請することは容易に考えられるはずだ。フライング休みを理由にしてしまったとしても意図していなかったならば3.4ヶ月の出場停止は特に重すぎる。
一方で問題視したいのは2020年7月に不正受給に関する注意喚起文書を全選手に通知していた後にも受給したという例があったこと。
通知日に全選手が確認できないことや、申請からのタイムラグがあったとしても、その後に受給があったということは協会の方針に背いたと言っても良いのではないだろうか。一般社会において会社の通知を無視するようなことがあれば極端な場合、解雇されることもある。理由はともあれ一定の期日以降に申請をしたことの方が問題ではないかと考える。
そして一番の問題点として、1度目の会見前に行われたアンケートの後から受給を自己申告してきた4名の選手。どの選手かというのは一切わからないが、更正第一として欲しいボートレースとしては(やむ得ない場合を除き)最も厳罰に処してほしい。全選手にアンケートを実施しているのであれば、その時点で嘘の申告をしていたのである。
意図的な受給でなかったとしてもこれによって非常に疑わしくなる。内訳の開示を求めるようなことはしないが非常に失望した。
極論を言えば4名のみ半年の出場停止で、その他については戒告でもよかったように感じてしまう。
まとめ
今回の不正受給問題で実名で上げられたのは井口佳典選手と山田康二選手のみ。
それ以外の選手については斡旋の取り消しなどで多くの選手に憶測が及んでいる。
しかし、実名で挙げられなかった以上、誤った選手に疑惑が及ぶことも考えられる。疑われていい気持ちは誰もがしないため、願わくば詮索しないで欲しい。それと同時にコロナ禍さえなければこのような問題も起きなかった。このままではロックダウンも視野に入り、ボートレースはもとより、あらゆる店舗や施設の閉鎖まで考えられる。感染防止対策の徹底と1日も早い撲滅に向けて皆様の協力をお願いしたい。
フネログ事務局
最新記事 by フネログ事務局 (全て見る)
- “BEE BOAT”は、信頼性が低い詐欺の悪徳予想サイトだ! - 2024年4月30日
- “ZABOON”は、捏造、虚偽、過大表現など何でもありの悪徳予想サイトだ! - 2024年4月18日
- “日刊予想競艇番付”は、中身のない虚偽で固めた詐欺予想サイトだ! - 2024年4月10日


 競艇選手による不正受給の処分について
競艇選手による不正受給の処分について



 おすすめの競艇予想サイト
おすすめの競艇予想サイト